たけち: ねぇ、さらら。XMLは構造テキストだって話をしたけど、XMLの元になったものって何だったか覚えてる?
さらら: あっ、うっ・・・なっ、なんだったっけ (^ ^;
たけち: あっ、いいんだよ。ちょっとからかってみただけ。SGMLってのがあったんだね。
さらら: あっ、そうそう。最初に聞いたんだったわね。きょうはそのお話なの?!

|
2001年6月10日(日)更新 |
|
たけち: ねぇ、さらら。XMLは構造テキストだって話をしたけど、XMLの元になったものって何だったか覚えてる? さらら: あっ、うっ・・・なっ、なんだったっけ (^ ^; たけち: あっ、いいんだよ。ちょっとからかってみただけ。SGMLってのがあったんだね。 さらら: あっ、そうそう。最初に聞いたんだったわね。きょうはそのお話なの?! |
|
■SGMLってなぁに?
|
たけち: SGMLは、いろいろなワープロやソフトウェアで作成されたドキュメント(文書)をできるだけ簡単に交換できるようにと考えられたものなんだ。 さらら: あら、ワープロ同士で交換ができなかったの? たけち: もちろん同じワープロで作ったドキュメントはそのまま交換できたけど、違う会社の作ったワープロで作ったドキュメントはそのままでは交換できなかったんだ。交換のためのソフトウェアも作られたけど、100パーセント完全には交換できなかったんだ。 さらら: へぇ〜。そうなんだ。。。SGMLだと100パーセント交換できるの? |
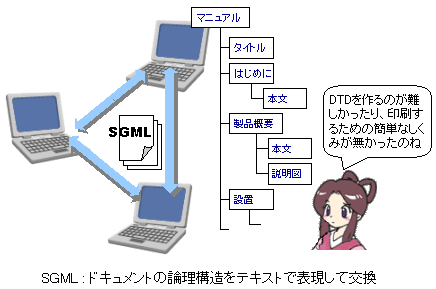
|
たけち: それが、そうじゃないんだ。 さらら: えっ、どっ、どうして? たけち: ドキュメントの「論理的な構造」を交換しようとしたのがSGMLなんだ。だから、「見栄え」については、ねっ。つまり、SGMLは「論理的な構造」に着目して作ったタグ付きのテキストを作るための規格なんだ。 さらら: あっ、そうなんだぁ。じゃあ、ドキュメントの50パーセントが交換できるってことなのね! たけち: あっ、うっ・・・・・ (^ ^; (ちっ、違うんだけど) |
|
■SGMLはどうなったの?
|
さらら: でも、どうして構造化テキストをあらわせるSGMLがXMLにとってかわられたの? SGMLってどうなったの? たけち: SGMLの代表的な応用としては、航空機や自動車などのマニュアルなどのドキュメントを作成・配布することが考えられ、そのために色々な応用規格が考えられ、企業もSGMLへの取り組みをしようと試みたんだね。特に米国で始まった活動が日本へも波及してきたんだ。 さらら: へぇ〜。なんだか大掛かりな印象を受けるわね。 たけち: そうした活動に引きづられて、企業からマニュアルなどの制作を受注している印刷会社にマニュアルなどのSGML化の指示が出されたりしたこともあったんだよね。だけど、マニュアルなどのSGML化は、ドキュメント情報からレイアウト情報を除いた論理情報の交換、ということから得られるメリットを十分理解・活用することができなかったんだ。 さらら: えっ、どうして?! たけち: たとえば商品なんかのマニュアルって、お客さまが見るものだよね。そうしたマニュアルの作成や配布・表示・印刷では、レイアウト情報が100%交換できないというデメリットが重要視しされすぎたために、当初の狙いのようには普及が進まなかったんだ。 |
|
たけち: それと、ドキュメントをSGML化するためには、その構造をDTDとして厳密に設計する必要があるんだけど、その作業には非常に大きな努力が必要だったんだね。そのことも普及への大きな障害になっちゃったんだ。 さらら: そうね。簡単なDTDの例を前に教えてもらったけど、それでも難しいものね。それで、もっと簡単に広くみんなに使ってもらえるようにって、XMLが考えだされたって事なのね。 たけち: そうなんだね。 →次へ (^ ^)v |

|
|
注): 今では、「レイアウト情報が100%交換できない」ことに目くじらをたてる人は少なくなりましたが、当時は大問題視されていたのです。 結局のところ、SGML化活動は、従来のレイアウト至上型のDTP(Desktop Publishing)ソフトウェア、たとえば、Quark Express, FrameMakerなどにSGMLが狙っていた構造化の機能が追加されただけの結果に終わっています。 ただ、XMLはSGML無しには生まれなかったでしょうし、SGMLでの歴史的な経験がかなりXMLに生かされていることも事実だと思います。 →次へ (^ ^)v |